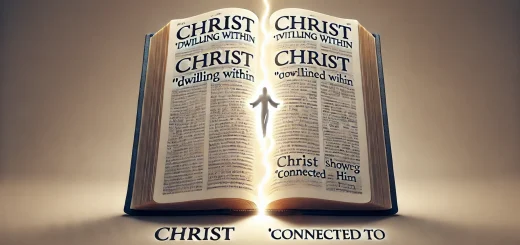「エホバ*の聖なる力*がある所には自由があります。」この訳はギリシャ語に忠実ですか?
第二コリント3:17
新改訳:「主は御霊です。そして、主の御霊がおられるところには自由があります。 」
新世界訳:「エホバは目に見えない方であり,エホバ*の聖なる力*がある所には自由があります」
この二つの聖書の訳し方には大きな違いがあります。「御霊がおられる」は聖霊が人格的存在として読み取ることが可能です。しかし、新世界訳では「聖なる力」と訳されておりその意味が大きく異なります。そこで、訳し方としてギリシャ語に忠実なのかどうか。ChatGPTに尋ねてみました。
第二コリント3:17新改訳 「主は御霊です。そして、主の御霊がおられるところには自由があります。 」 ここでいう「主は御霊です。」とはギリシャ語の言語的にはどのような意味がありますか?
ChatGPT:
第二コリント3:17の「主は御霊です。」(κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν)のギリシャ語について、言語的な観点から解説します。
1. ギリシャ語の構造
κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν
- κύριος (kyrios):「主」
- τὸ πνεῦμά (to pneuma):「霊」(定冠詞 τὸ がついているので、特定の「霊」を指す)
- ἐστιν (estin):「~である」(動詞「ある、存在する」の現在形)
この構文は A = B の等式を表す文章(叙述文)であり、直訳すると 「主は霊である」 となります。
2. 「主」とは誰を指すのか?
ギリシャ語原文において「主」(κύριος)は通常、文脈によって父なる神・キリスト・聖霊のいずれかを指します。
ここでは、直前の文脈(第二コリント3:14-16)を見ると、「主」はキリストを指していることが明らかです。特に16節では「人が主に向くなら、その覆いは取り除かれる」と述べられており、この「主」はイエス・キリストと解釈されます。
したがって、「主は御霊です。」は 「主(キリスト)は霊である」 という意味で理解されます。
3. 言語的な意味と神学的解釈
この表現は単純に「主=聖霊」という意味ではなく、文脈的に以下のように解釈されることが多いです。
- キリストと聖霊の密接な関係
- キリストは「御霊(聖霊)の働きを通して現れる方」である。
- キリストは復活後、霊的な存在として私たちとともにおられる(1コリント15:45「最後のアダムは命を与える霊となった」参照)。
- 新しい契約の自由
- 文脈では、旧約の「石の板に書かれた律法」と、新約の「霊による自由」が対比されている(第二コリント3:6-8)。
- キリストのもたらす救いは、単なる文字(律法)ではなく、聖霊による新しい命の働きである。
したがって、言語的には「主(キリスト)は霊(=聖霊の働きを通して現れる存在)である」という意味になります。
4. まとめ
- ギリシャ語構造:「主(κύριος)=霊(τὸ πνεῦμά)」を示す叙述文
- 「主」はキリストを指す
- 「霊」は聖霊の働きを意味し、新しい契約の自由を強調
- 「主は御霊である」とは、キリストが聖霊を通して信者と共におられることを示唆
この節はキリスト論と聖霊論の接点を示す重要な表現であり、単純に「キリスト=聖霊」という意味ではなく、「キリストが聖霊を通して私たちに働きかける方である」ということを示していると言えます。
あなた:エホバの証人の新世界訳では以下の様に訳されています。
スマホアプリ(1985版?)
「さて、エホバは霊です。そしてエホバの霊のある所には自由があります。 」
新世界訳(2019年改訂版)
エホバは目に見えない方であり,エホバ*の聖なる力*がある所には自由があります+。 これは訳し方としてどうですか?
ChatGPT:
エホバの証人の**新世界訳(NWT)**における第二コリント3:17の訳し方について、言語的・神学的な観点から検証します。
1. 1985年版(スマホアプリ)
「さて、エホバは霊です。そしてエホバの霊のある所には自由があります。」
(1) κύριος(キュリオス)を「エホバ」と訳すことについて
- 原文の κύριος (kyrios, 主) は、一般的には 「主(キリスト)」 を指します。
- 文脈的にも、3:14-16では「主」がキリストを指しており、いきなり「エホバ(ヤハウェ)」に置き換えるのは恣意的な翻訳です。
- エホバの証人は「主」が旧約聖書のヤハウェを指す場合、強引に「エホバ」に置き換える傾向がありますが、ここではそのような用法とは異なります。
(2) 「エホバの霊」=「聖霊」と訳している点
- 原文の「τὸ πνεῦμα(to pneuma, 霊)」は定冠詞付きなので、特定の霊を指します。
- 直訳:「主は霊である」(κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν)であり、「主の霊」ではありません。
- 「エホバの霊」と訳すと、あたかも「霊」はエホバ(ヤハウェ)の所有物のように読めますが、ギリシャ語の構造はそうではなく、「主(キリスト)が霊である」と言っています。
📌 結論:
1985年版の訳は不正確であり、意図的な神学的解釈が入り込んでいると考えられます。
2. 2019年改訂版
「エホバは目に見えない方であり,エホバの聖なる力がある所には自由があります。」
(1) 「主は霊です」を「エホバは目に見えない方」とする変更
- 「霊」(πνεῦμα)を「目に見えない方」と訳すのは不自然
- 「霊(pneuma)」=「目に見えないもの」 というのは、NWT独自の解釈であり、ギリシャ語の直接的な意味とは異なります。
- もしも「目に見えない方」と訳すなら、「神は霊です」(ヨハネ4:24)と訳すべきですが、ここでは「主(キリスト)」について述べています。
- 「主(キリスト)は霊である」という原文の意味をねじ曲げて、ヤハウェにすり替えた訳になっている。
(2) 「聖なる力」とは?
- 「τὸ πνεῦμα」を「聖なる力」と訳すのは、エホバの証人独自の神学的解釈
- 一般的なキリスト教神学では「霊(pneuma)」=「聖霊(Holy Spirit)」を指しますが、エホバの証人は聖霊を人格的存在と認めていないため、「力」と訳しています。
- しかし、ここで「霊」は聖霊だけでなく、キリストの働きを指しているため、「力」と訳すと意味が限定されすぎます。
- 文脈的には、キリストが霊的に臨在することを示しているため、「聖なる力」は誤訳に近い。
📌 結論:
2019年版は1985年版よりもさらに翻訳の改ざんが進んでおり、原文の意味を完全に歪めている。特に、キリストを「霊」と表現することを避けるために「目に見えない方」と置き換えた点は、意図的な神学的改変と言えます。
3. 全体の評価
| 訳 | 「主」(κύριος)をどう訳したか? | 「霊」(τὸ πνεῦμα)をどう訳したか? | 正確性 |
| 原文(ギリシャ語) | 主(キリスト) | 霊(聖霊、霊的な存在) | ✅ |
| 新改訳(プロテスタント訳) | 主 | 御霊 | ✅(正確) |
| 新共同訳(カトリック・プロテスタント共通) | 主 | 霊 | ✅(正確) |
| 1985年版(NWT) | エホバ | エホバの霊 | ❌(意図的な改変) |
| 2019年版(NWT) | エホバ | 聖なる力 | ❌(大きく改変) |
4. まとめ
- 「主(κύριος)」を「エホバ」とするのは誤訳
- 文脈的に「主」はキリストを指すのが自然。
- ここで「エホバ」にするのは、エホバの証人の神学的前提による改変。
- 「霊(τὸ πνεῦμα)」を「エホバの霊」や「聖なる力」と訳すのは不自然
- 原文では「主=霊」という等式があるが、それを避けるために意味を変更している。
- 2019年版は1985年版よりもさらに原文の意味をねじ曲げている
- 「霊」を「目に見えない方」と訳すことで、キリストの霊的な臨在の意味を消している。
結論 新世界訳の第二コリント3:17は、原文の意味を大きく歪めた翻訳です。特に2019年版は、キリストと聖霊の関係を完全に消去する意図的な改変が施されているため、言語的・神学的に見て非常に不正確な訳といえます。