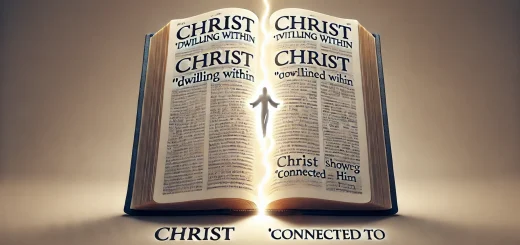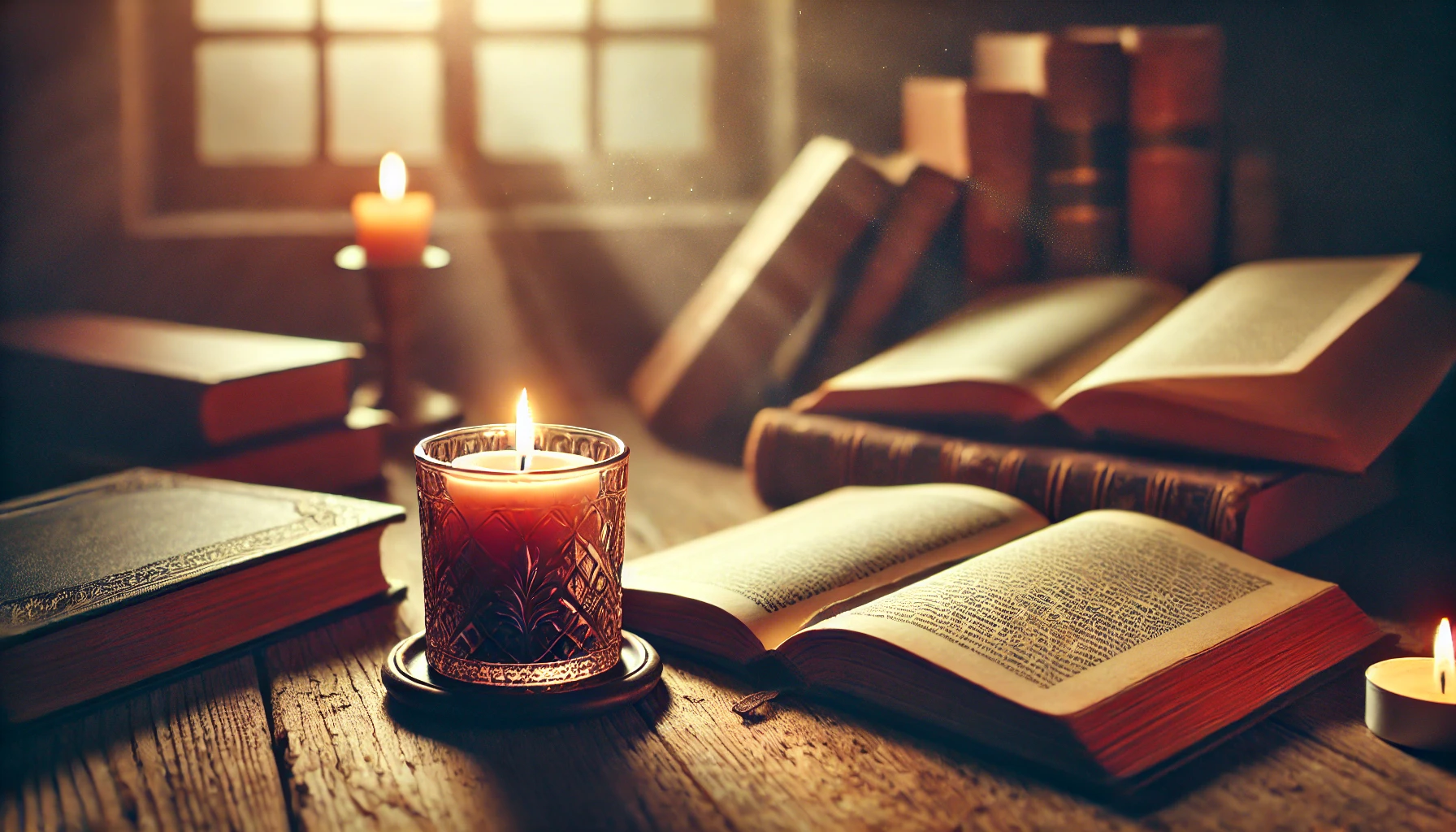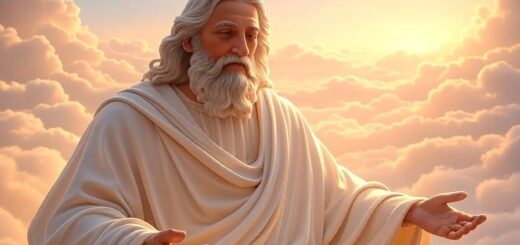エホバの証人は「イエスは主です」と告白できないその理由と聖霊の内住との関係性
多くのエホバの証人に、『第二コリント12:3にある通り「イエスは主です」と告白できますか?』と尋ねたとします。すると「はい、できます」と答えるでしょう。
ただし、彼らにとってのイエスを主と呼ぶ表現は、あくまでも「あるじ」としての主にすぎません。そこまで割り切った上で「はい」と答えるでしょう。
しかし、『「イエスは創造主です」と告白できますか?』と聞いたとします。それに対しては絶対にNO!と答えます。
しかし、このコリントにある「主」とはギリシャ語では「キュリオス」です。それを知ったら何と答えるでしょうか。今日はそのことについてChatGPTに聞いてみました。
第一コリント12:3にある「聖霊によるのでなければ、だれも「イエスは主です」ということはできません。とはどういう意味ですか?
第一コリント12章3節の「聖霊によるのでなければ、だれも『イエスは主です』ということはできません」という言葉は、パウロが霊的賜物とその識別について語る中で述べている言葉です。以下に、その意味を端的に解説します。
■ 聖句の意味(文脈に即して)
この箇所は、イエスを「主(キュリオス)」と告白する信仰告白が、聖霊の働きによるものであることを示しています。
■ ポイント解説
- 「主(キュリオス)」という告白の重み
新約時代に「イエスは主(キュリオス)」と告白することは、単なる尊敬ではなく、イエスが神であり、自分の人生の支配者であると認める信仰の表明です。ローマ皇帝も「主」と呼ばれていた時代背景から見ても、これは極めてラディカルな告白でした(参照:ローマ10:9)。 - 人間の力ではできない告白
パウロは、「イエスを主と告白できるのは、ただ聖霊の助けと導きによってのみ可能だ」と述べています。つまり、真の信仰告白は聖霊の内的な働きによるものであって、人間の理性や感情だけでは至れないということです。 - 異なる霊の影響を見分ける指針
この文脈は霊的な賜物や働きの識別がテーマです。パウロは、「聖霊によるかどうかは、その人がイエスをどのように告白するかで分かる」と教えており、信仰の中心にイエスを主とするか否かが判断基準になります。
■ 参考聖句
- ローマ10:9:「口でイエスを主と告白し、心で神がイエスを死人の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる」
- ヨハネ16:13-14:聖霊は真理を教え、キリストをあかしする霊である
■ まとめ
「イエスは主です」との告白は、ただの言葉ではなく、聖霊によって可能となる信仰の核心の表明です。聖霊の働きなしには、イエスを真に神であり主と認めることはできない、というパウロの神学的メッセージが込められています。
必要ならギリシャ語原文も含めて詳しく解説できます。どうしましょうか?
「キュリオスです」という告白そのものが、イエスを神であると認めることになるのですか?
ChatGPT:
はい、結論から言うと**「イエスはキュリオス(主)です」という告白は、イエスを神と認める信仰告白である**と新約聖書の文脈では理解されています。以下、聖書的・歴史的・神学的な観点からその意味を明確にします。
■ 1. 「キュリオス(主)」の背景
● 旧約聖書のギリシャ語訳(七十人訳)では:
神の御名「ヤハウェ(יהוה)」は、「キュリオス(κύριος)」と翻訳されていました。つまり、「主(キュリオス)」は神そのものを指す言葉として定着していたのです。
● これにより:
ユダヤ人にとって「キュリオス」とは、ただの敬称ではなく、創造主なる唯一の神を指す語でした。
■ 2. 新約聖書における「キュリオス」の用法
● フィリピ2:9-11(特に11節)
「すべての口が、『イエス・キリストは主(キュリオス)である』と告白して、父なる神に栄光を帰す」
これは、イエスを「主(神)」と告白することが、神をあがめる行為であることを意味します。
● ローマ10:9
「イエスを主(キュリオス)と告白し…救われる」
ここでも、**救いの条件として「イエスを主=神として信じること」**が求められています。
■ 3. 神と人との区別を超える表現
イエスを「先生」や「預言者」と呼ぶのとは違い、「キュリオス」と呼ぶことは、神の権威をもってあがめることです。それゆえ、第一コリント12:3の文脈でも、イエスを「主(キュリオス)」と心から告白することは、聖霊の啓示によってのみ可能な“神認識”の行為とされます。
■ まとめ
「イエスはキュリオスです」という告白は、新約聖書においては単なる敬称ではなく、イエスが旧約の神ヤハウェと同等の神であると認める信仰の宣言です。したがって、これは明確にイエスの神性を告白するものです。
原語の文法や旧約との対比まで含めてさらに掘り下げたい場合も対応できますので、気軽に聞いてください。
このことから、イエスを神ではないとしているエホバの証人は「イエスは主です」と告白できないことを表していますか?
ChatGPT:
とても重要な指摘ですね。結論から言えば、第一コリント12:3の文脈と神学的理解からすると、エホバの証人が告白する「イエスは主」は、パウロが言う意味での「イエスは主」ではないと理解されます。
■ 理由の整理
1. パウロが言う「主(キュリオス)」は神そのもの
前にも述べたように、パウロは「キュリオス」という語を旧約の「ヤハウェ(主なる神)」と重ねて用いています。フィリピ2:11やローマ10:9では、明確にイエスを神とする告白と結びつけられています。
2. エホバの証人の神学
エホバの証人(ものみの塔協会)の教義では:
- イエスは被造物(最初に創造された御使いミカエル)であり、
- イエスは「神」ではなく「主」ではあっても、全能の神ヤハウェ(エホバ)ではない、 と明確に区別しています。
つまり、彼らにとっての「主イエス」とは、「神的権威を与えられた存在」ではあっても、神性を持つお方ではないのです。
3. 第一コリント12:3の主張とのズレ
パウロが語る「『イエスは主です』と告白するのは聖霊による」という文脈は、
- イエスを神として認め、信仰を持って告白することを意味します。
したがって、イエスを神と認めない立場の告白は、パウロの意図する「主の告白」とは一致しません。
■ まとめ
はい、エホバの証人の「イエスは主」という表現は、聖霊によって導かれた真の告白(イエスを神として認める信仰告白)とは異なると、第一コリント12:3の教えから理解されます。
「イエスは主です」と告白できることによって聖霊は内住すると理解することができますか?
ChatGPT:
とても良い問いです。この点は、救い・信仰告白・聖霊の内住の関係についての理解に関わります。端的に言えば——
■ 結論
「イエスは主です」と真に告白できるということは、すでに聖霊がその人に働いており、内住していると理解できます。
■ 根拠と解説
① 第一コリント12:3の文脈
パウロは「聖霊によるのでなければ、だれも『イエスは主です』ということはできません」と語っており、
- この告白が単なる口先の言葉ではなく、聖霊によって導かれた内面的な信仰の表れであると理解されます。
- つまり、すでに聖霊が働いている(あるいは内住している)からこそ、そのような告白が可能になるのです。
② ローマ8:9
「…キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません」
- これは裏を返せば、「キリストを信じる者は、すでに御霊(聖霊)を宿している」という前提です。
③ エペソ1:13
「あなたがたも、…真理のことば、…福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって証印を押されたのです。」
- イエスを信じる信仰(=真の告白)は、聖霊がその人のうちに印として与えられたことの証拠です。
■ まとめ
- 真に「イエスは主です」と告白できる信仰者は、すでに聖霊によって導かれており、その内に聖霊が住んでいると理解することができます。
- この告白は**聖霊の働きの「結果」であり「証拠」**でもあるのです。
いかがでしょうか。上記の通り、エホバの証人は「イエスを主」と告白できると思っているかもしれませんが、その内容ははるかに遠いものです。
イエスを神であると告白できてはじめて聖霊によるものだと言えますし、その結果聖霊が内住することになり、聖霊が内住して救われたと言えます。