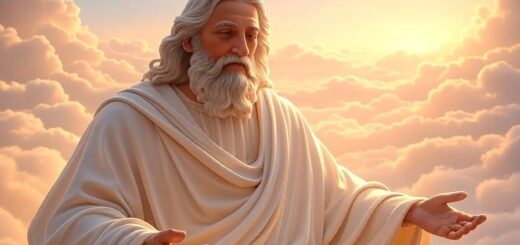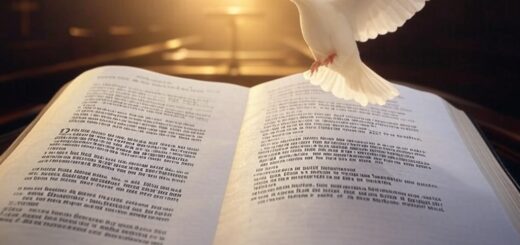キリストが心のうちに住むことは救われている人の特徴
私たちは、信仰告白をしたときに心のうちにイエス・キリストをお迎えしました。なぜお迎えできるのでしょうか。それは聖霊が私たちを信仰告白へと導き、私たちのうちに内住してくださるからです。その結果として、イエス・キリストも心のうちに住んでくださるのです。これこそ救われた人の最大の特徴といえます。
同時に、聖霊がうちに住んでくださることによって救われるためには、イエス・キリストを神として認める必要もあります。なぜなら、三位一体なる神様として受け入れることができて初めてイエス・キリストが心のうちに住むことも受け入れることができるからです。
今日はそのことが書かれている聖書箇所を見てみましょう。
第二コリント13:5「自分のうちにイエス・キリストがおられることを、自覚していないのですか。」
この聖句では「自分のうちにイエス・キリストがおられる」と表現されています。一般的にはここを読んだ時に、素直に心のうちにおられると解釈できるでしょう。
しかし、エホバの証人はそのように解釈できない神学的構造の中におかれています。
では、彼らがどのようにしてこの聖句を読むのか、そしてなぜこの聖句が重要な意味を持つのかを一緒に観てみましょう。
第二コリント13:5「自分のうちにイエス・キリストがおられる」とありますが、これは人の心の中におられるということを意味していますか?
ChatGPT:
第二コリント13:5の「自分のうちにイエス・キリストがおられる」という表現について、これは「イエス・キリストが信者の心の中におられる」という意味を含んでいると考えられます。しかし、それだけではなく、より広い神学的な意味を持っています。
文脈から見る意味
第二コリント13:5は、パウロがコリントの信徒たちに対して「あなたがたが信仰に生きているかどうかを試し、吟味しなさい」と勧めている部分です。ここで「イエス・キリストがあなたがたのうちにおられる」ことを確認するように促しています。
この「うちにおられる」という表現は、ギリシャ語では ἐν ὑμῖν (en hymin) で、「あなたがたの中に」「あなたがたの間に」と訳すことができます。ここから、少なくとも以下の2つの解釈が可能です。
- 個人的な内的臨在(信者の心の中)
- ローマ8:10「キリストがあなたがたのうちにおられるなら、…」
- ガラテヤ2:20「もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる」
これらの聖句と同様に、信者の内側にキリストが住んでおられることを指すと考えられます。つまり、聖霊によるキリストの臨在が信仰者の心の中にあるという意味です。
- 共同体としての臨在
- マタイ18:20「二人または三人が私の名によって集まるところに、私もいる」
- コロサイ1:27「異邦人の間にあるこの奥義の栄光の望みは、あなたがたのうちにおられるキリストである」
ここでの「うちに」は、信仰共同体の中にキリストが臨在していることを示している可能性もあります。
まとめ
したがって、「イエス・キリストが自分のうちにおられる」というのは、信者一人ひとりの心の中におられること(内的臨在) と同時に、教会共同体の中におられること(共同体の臨在) の両方の意味を含むと考えられます。
あなたが具体的にどの側面を気にされているかによって、もう少し掘り下げて解釈することも可能です。
新世界訳では「イエス・キリストがあなたがたと結びついておられる」とあります。この訳ではどのように解釈される可能性がありますか?
ChatGPT:
新世界訳が「イエス・キリストがあなたがたと結びついておられる」と訳している点は、原文の「ἐν ὑμῖν (en hymin)」の解釈によるものです。この訳し方では、「キリストが信者の内におられる」というよりも、「信者とキリストの関係性」に重点が置かれていると考えられます。
1. 新世界訳の訳し方の特徴
新世界訳はエホバの証人の公式訳であり、神学的な意図をもって翻訳されていることが多いです。特に「キリストが信者の内に住む」という概念を避ける傾向があるため、「結びついておられる」という訳を採用したと考えられます。
- 「結びついておられる」は、「内に住む」という意味よりも、「関係性」や「一致」を強調する表現です。
- これは、エホバの証人の神学的立場において、キリストが「信者の内に住む」ことよりも、「信者がキリストと共に歩む」という関係を強調する傾向があるためと考えられます。
2. この訳での解釈の可能性
「キリストがあなたがたと結びついておられる」という訳をとる場合、以下のような解釈が可能です。
(1) 信者とキリストの関係性の強調
- これは、信者がキリストと結びついている状態、つまり「キリストの教えを守り、従っていること」を意味する可能性があります。
- ヨハネ15:4「私にとどまりなさい。そうすれば、私はあなたがたにとどまります」にあるように、「とどまる」「結びつく」という関係的な意味を強調していると考えられます。
(2) 共同体としての結びつき
- この表現は、「信者の群れ全体がキリストと結びついている」ことを示す可能性もあります。
- これは「キリストが個々の信者の内に住む」よりも、「教会全体がキリストに属している」ことを強調する解釈につながります。
3. 他の訳と比較した神学的影響
- 「イエス・キリストがあなたがたのうちにおられる」(新改訳、口語訳など)
→ キリストの「内的臨在」を強調し、信者がキリストによって生かされていることを示唆。 - 「イエス・キリストがあなたがたと結びついておられる」(新世界訳)
→ キリストが信者の内に住むというより、「キリストと共に歩むこと」「結びつきを持つこと」を強調。
4. 結論:どちらの訳が適切か?
- 原文の「ἐν ὑμῖν (en hymin)」は通常「あなたがたのうちに」と訳されるため、新世界訳の「結びついておられる」は意訳的な要素が強いと言えます。
- ただし、新世界訳の解釈にも一定の妥当性があり、特に「キリストとの関係性」を強調したい場合にはそのような訳もあり得ます。
- しかし、聖書全体の文脈(ガラテヤ2:20、ローマ8:10など)を考えると、「キリストが信者のうちにおられる」という解釈のほうが自然だと考えられます。
もし新世界訳の解釈についてさらに深掘りしたい場合、関連する聖句(特にエホバの証人がどのように「キリストの臨在」を理解しているか)を比較してみるのも良いかもしれません。
エホバの証人の場合は三位一体を信じていません。よって、キリストが信者のうちに住んでいるという認識を避けなければならないとの立場を取っていると考えられますか?
ChatGPT:
はい、そのように考えることができます。エホバの証人は三位一体を否定し、イエス・キリストを「創造された神の子」として位置づけているため、伝統的なキリスト教の「キリストの内的臨在」の教えとは異なる立場を取っています。そのため、「キリストが信者のうちに住んでいる」 という表現を避ける傾向があるのは、神学的な理由によるものと考えられます。
1. 三位一体を否定する立場と翻訳の影響
エホバの証人は、イエスを神(エホバ)と同格の存在とは見なさず、エホバに従属する被造物(大天使ミカエルと同一視されることもある) としています。このため、伝統的なキリスト教で強調される「キリストが信者の内に住む」という概念をそのまま受け入れることは難しくなります。
新約聖書では、キリストが信者のうちに住むことを示唆する表現が多くあります(例:ローマ8:10、ガラテヤ2:20、エペソ3:17)。しかし、もしこの表現をそのまま受け入れると、キリストの神性や聖霊と同じような働きがあるかのような解釈につながるため、エホバの証人の神学とは相容れません。そのため、「キリストがあなたがたと結びついておられる」 という訳を採用し、キリストが信者の「内に住む」のではなく、外から導く存在であるかのように表現を調整 したと考えられます。
2. 新世界訳の翻訳傾向と神学的意図
エホバの証人の翻訳である新世界訳は、エホバの証人の教義に一致するように翻訳されていることが指摘されています。たとえば:
- ヨハネ1:1 で「ことば(ロゴス)は神であった」を「ことばは神のような者であった」と訳す(キリストの神性を否定)。
- コロサイ1:16-17 で「すべてのものは彼によって造られた」を「すべての[ほかの]ものは彼によって造られた」と、「ほかの」 を挿入(キリストが被造物の一部であるかのように強調)。
- ルカ23:43 で「あなたは今日、私とともにパラダイスにいる」を「今日、あなたに言います。あなたは私とともにパラダイスにいるようになる」と訳し、死後すぐに天国に行くという概念を避ける。
このような翻訳の傾向を考慮すると、「キリストが信者の内に住む」という表現がもたらす神学的な影響を避けるために、「キリストがあなたがたと結びついておられる」と訳した可能性が高い です。
3. エホバの証人のキリスト観と「結びつき」の意味
エホバの証人の教義では、信者がキリストとどのように関係するかについて、「従う」「模範にする」「信仰を通じてつながる」 という表現を好みます。つまり:
- キリストは信者の「内に住む」存在ではなく、外から導く指導者・王である。
- 信者はキリストに「従う」「一致する」ことが求められる。
- 信者はキリストと霊的一致を持つが、それは「信仰的な結びつき」であり、キリストが「内的に住む」という意味ではない。
このため、新世界訳では「キリストがあなたがたと結びついておられる」という訳を採用し、「キリストの内的臨在」ではなく、「キリストとの関係性」に焦点を当てた可能性が高いです。
4. 伝統的なキリスト教との違い
伝統的なプロテスタント神学やカトリック神学では、「キリストが信者のうちに住む」という概念は、聖霊の働きを通じた霊的な臨在 として理解されます。例えば:
- ガラテヤ2:20 「もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる」
- エペソ3:17 「こうして、信仰によってキリストがあなたがたの心の内に住んでくださるように」
これに対し、エホバの証人の教義では、聖霊は「神の活動力」であり人格を持たないため、「キリストが信者のうちに住む」という概念自体が彼らの神学とは整合しません。そのため、翻訳においても意図的に異なる表現が採用されたと考えられます。
結論
エホバの証人は三位一体を否定しているため、キリストが信者のうちに住むという概念を避ける必要があり、その結果、新世界訳では「キリストがあなたがたと結びついておられる」と訳したと考えられます。これは単なる翻訳の違いではなく、神学的な意図を反映した訳 であり、彼らの教義と一致するように調整されていると見ることができます。
もしこの点をさらに深く比較したい場合、他の翻訳と並べて読むことや、ギリシャ語原文のニュアンスを調べることも有益かもしれません。
いかがでしたか。彼らは自分たちこそ真のキリスト教であり、自分たちだけがハルマゲドンを通過して救われると信じています。しかし、イエス・キリストを心のうちにお迎えするという祈りをしたことがありませんし、絶対にできません。イエス・キリストは被造物であると信じているからです。被造物は心の中に住むことができないからです。
しかし、これは同時に神である方を神としないということであり、創造主を創造主として認めないことです。
果たしてそれで救いを受けることはできるのでしょうか。救われていないのであれば、そうさせているものは一体何でしょうか。